その痛みは我慢しなきゃいけない?
もうすぐ第九シーズン。
ベートーヴェンのシンフォニーには
「16分音符で延々と刻む」がたくさん出てきます。
「のだめ」でブレイクしてから演奏機会の増えた「ベト7」
根強い人気で繰り返される「エロイカ」
超・定番の「運命」
意外と激しい「田園」
ユーモアにあふれた「ベト8」
などなど……
そういえば、刻みやトレモロが大変なのはベートーヴェンだけでもないですね。
(ブルックナーとか……)
ところで。
演奏を終えたあとにこんな経験はありませんか?
「肩の後ろが痛い」
「肘がしびれる」
「指がガチガチ」
「つま先がしびれる」
「腰が痛い」
「目の奥が重い」
「あごがガクガクする」
「首が固まる」
お風呂で温めたり、マッサージでほぐしてもらったりするのは気持ちいいですね。でも、次の演奏では、また同じ痛みが出てくる……演奏を続ける限り悩み続けなければいけないのでしょうか。
お風呂やマッサージで得られるいやしの時間・憩いのひとときは演奏したことへのごほうびですよね。疲れや痛みから開放されるのも、これまた嬉しいことです。
ちょっと思い浮かべてみてください。そもそも痛まなくなるとしたらどうでしょう。お風呂やマッサージは、さらにゆったりと楽しめます。シップや痛み止めのお世話になることも減っていくでしょう。
凝り固まった身体でする演奏と、ほぐれた身体でする演奏。どちらのほうが、自由な表現に近づきやすいでしょうか?
ベートーヴェンは言いました。
苦悩を突き抜けて、歓喜に至れ
これって、音楽の喜びを得るためには体の痛みを我慢しろという意味でしょうか?
私・いちろーたが学んでいるアレクサンダーテクニークを使うと、自分で自分を固めていることに気づきやすくなっていきます。
もともと教わっていたバイオリンの師匠・カナメ先生のメソッドによって、バイオリン演奏を合理的に習得してきましたが、アレクサンダーテクニークを重ねあわせたことで、より明確に「身体と楽器の奏法」を自分でできるようになってきました。
トレモロでの肩・脇の痛みをやめるために私・いちろーたがやったことは何でしょうか。
それは、
「弓を動かすために、背中も動いていい」
というものでした。
バイオリンから音を取り出すためには、弓の毛を弦とこすり合わせる必要があります。そのためには、弓が動けるように腕を動かす必要があります。腕を動かせるように、胴体を動かせる必要があります。胴体が動けるように足が支えてくれている必要があります。これら全部が動かせるように、頭が動けるようにしておくのです。
このなかの、どれかひとつが抜けたときに「身体を固める」ということが起きていたのです。
身体を固めるのをやめるために、できることの根本が「頭が動けるようにする」ということです。そして、それを思い出す方法は、ひとそれぞれ、状況それぞれに応じて創りだすことができます。
このやり方を、いろんな状況に合わせてレッスンしています。
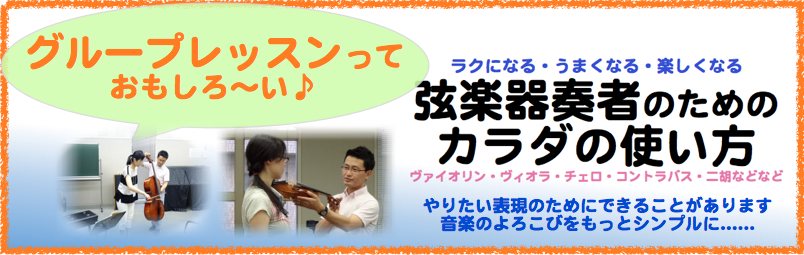
私の考え方は、ブログの200近い記事の中でも紹介していますし、メールマガジンに登録すれば私・いちろーたのセミナー開催のお知らせや、新しく発見したことのご紹介などを毎月数回に分けてメールでお届けします。
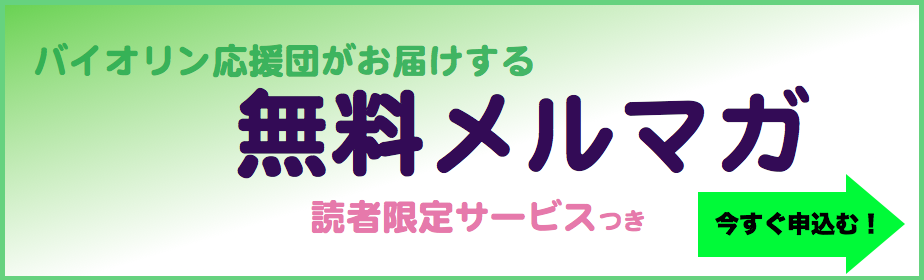
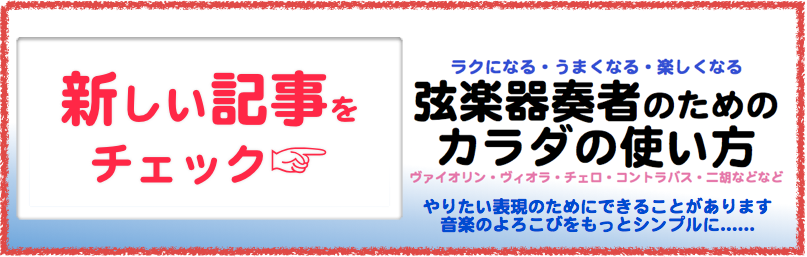
無料でダウンロードできる小冊子もご用意しました。文字だけでは伝わりにくいコツもあるので、YouTube動画も用意してあります。


無料でお届けしている情報がありますので、どんどん試してみてください。
あなたの音楽生活が、よりラクに、より自由に、より豊かな喜びにあふれたものになることを願いつつ。
2013年11月 バイオリン応援団☆いちろーた
音楽の悩み、ひとりで抱えていませんか?
もしあなたが、
- 音は出るけど、なぜか響かない
- 練習しているのに上達している気がしない
- 正しい構えをしてるはずなのに、しんどい
そんなふうに感じているなら──
メルマガ『バイオリン応援団通信』を読んでみてください。
毎日ちょっとずつ、
演奏の本質に近づいていく考え方や練習のヒントをお届けしています。
いちろーた式の学びは「深く考えさせられるのに、すっと身につく」
今まで読んだどの教材とも違うかもしれません。
👇メルマガ登録はこちらから
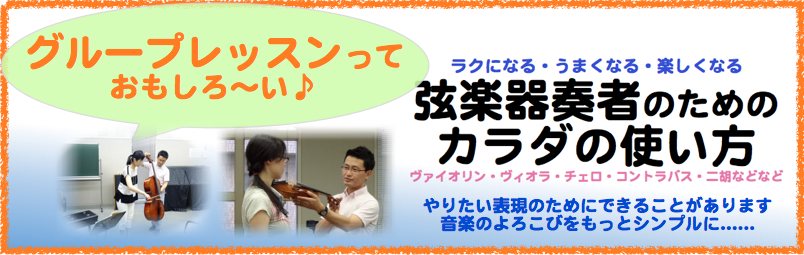

コメント