音階練習も指が音列のパターンを覚え、指の動きや並びを体が覚えることで、どの調の曲でも弾けるようになります。
篠崎史紀さんのヴァイオリン上達教材サイト 『ヴァイオリン上達のコツ』http://www.violinjp.com/violin/jyoutatu.html より
そのとおりです!大賛成!
ところで、バイオリンの左手指トレーニングは、ほとんどの場合《第1ポジション》から始めます。なぜでしょうか?
左手指のトレーニングを《第1ポジション》から始める2つの理由
- 指を広げる動きを学ぶのに適している
- 指を配列する位置と音程のズレ具合がもっともゆるやかである
この2つこそが、私が左手指のトレーニングを第1ポジションから始める理由として自分に言い聞かせていることです。
第1ポジションは「指を動かす」ための基本をすべて学べる
弦楽器奏者が左手の指先を動かす目的
ヴァイオリニストをはじめ、チェロや二胡もふくめて、弦楽器奏者が左手指を動かすのはなんのためでしょうか?
それは、弦に触れて、弦がふるえるときの条件を操るためです。
腕の機能をフル活用しよう
第1ポジションでは、腕の機能をフル活用することを学びます。
ヴァイオリンやヴィオラの場合は、体幹から遠く離れたところに指先を届けることになります。チェロや二胡ではどうでしょうか?体幹に近いような遠いような、複雑ですね。でもだいじょうぶ、本当はシンプルです。
ちょっとだけ練習方法の紹介をしますね
どの楽器だったとしても基本はシンプルです。楽器を持たずに、「もしも楽器を持ったとしたら、このあたりに指先が来て欲しい」という場所を思い浮かべます。その場所へ指先を運びます。これだけです。ポジションを移動しようというときも同じように動かします。
この《動かしたい物の軌跡を描くようにする》動かし方こそが、フィンガリング習得のカギです。この動かし方は、実際に楽器をもって演奏する・練習するときにも有効です。※リーディングエッジとは……関連記事その1・その2
《第1ポジション》は音程の反応がおだやか
第1ポジションでは、指の動きに対する音程の反応がおだやかです。
ポジションが高い方へ移っていくと、同じような指先の動きでも、音程が敏感に変わるようになります。
大きな的を狙ってボールを投げるよりも、小さな的を狙ってボールを投げるほうが、細かいコントロールが必要になるのと似ています。
左手と楽器の関係はこうして作る
《指に音列を覚えさせる》ためには、まず、どう動かすと音が高くなるのか、低くできるのかを学ぶことです。弦に触れたり、離したりを繰り返していくことで「この音程が欲しかったら、この場所に触れればいい」という音列と体の動きの関係性が、まるで地図のように出来上がっていきます。これが《指に音列を覚えさせる》とか《指の形を覚える》ということです。
この基本形からどのように発展させていくかが、バイオリンやそれぞれの楽器の教師たちの知恵の見せどころとなります。世の中に出回っている音階教本が似ているようで、ちょっとずつ違うのは、こうした《音列とカラダの関係》をどのように考えているかが、教師ごとに違っているからです。
音階練習はお好きですか?
私のバイオリンの先生の自慢は「弟子たちがみんな、ヒマを見つけるとすぐに音階練習をやり始めること」です。音列とカラダの関係を学び、その効能を初心者の時からみっちり味わっているからです。
ひとつ言っておくと、すべての調性での指遣いを丸暗記する必要はありません。カール・フレッシュだって《生徒がハ調しか練習しない》からすべての調性での練習パターンを仕方なく書き起こしたんです。詳しくはレッスンで。※カール・フレッシュ=ヴァイオリンの音階練習体系で有名(上記Amazonリンク参照)まえがきには素晴らしいことが書いてあるのに、残念なことにその音階教本のおせっかいさが災いして、世の中の音大生からは疎まれています。かわいそうに!!
音楽の悩み、ひとりで抱えていませんか?
もしあなたが、
- 音は出るけど、なぜか響かない
- 練習しているのに上達している気がしない
- 正しい構えをしてるはずなのに、しんどい
そんなふうに感じているなら──
メルマガ『バイオリン応援団通信』を読んでみてください。
毎日ちょっとずつ、
演奏の本質に近づいていく考え方や練習のヒントをお届けしています。
いちろーた式の学びは「深く考えさせられるのに、すっと身につく」
今まで読んだどの教材とも違うかもしれません。
👇メルマガ登録はこちらから



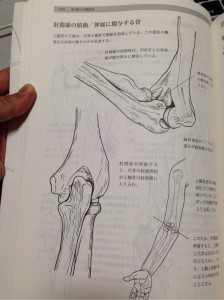
コメント