ほんとは数を増やしたくないんですが、「もうちょっと細かく教えて欲しい!」という声もいただくので、7つだけ書き出します。一覧にしておくので演奏がうまくいかないときや、教え方に困ったときに眺めてみてください。
弦楽器奏者に役立つ身体の基本7項目
- 頭は背骨の上に乗っかっていて、自由に動ける
- 頭の下には首の骨が7本続いている
- 腕は体の前についている
- 手のひらは指だ
- 筋肉の仕事は縮むこと
- 動きの先端を思い描く
- 足も自分だ
ほんのちょっとだけ説明を付け加えておきます。
弦ラク*身体の基本1. 頭が動ける
頭は背骨の上に乗っかっていて、自由に動ける
脊椎動物は、頭が動きの先端になっています。さかな、かえる、へび、いぬ、さる、きじ……。みんな、頭が動きをリードしています。
ただ、人間の姿勢だけが、「頭が動きをリードしている」ようには見えにくいですね。人間は、他の動物と決定的に違っていて「直立二足歩行」を採用しているからです。歩き始めたころの子供を観察するとよくわかります。立つときも、歩くときも、走るときも、何かに手を伸ばそうとするときも、いつも頭が動き始めてから、身体のあちこち全部が目的に応じて頭を支えるための最善の組み合わせで動きを創りだしています。
成人男性の頭の重さは5キログラムを超えるそうです。頭の重さを支えることは、二足歩行システムに任せちゃったんですね。二本の前足は歩行システムから解放され、腕として自由な活動を担当できることになりました。
自分のカラダに遠慮せず遊ぼう
自分の身体です。せっかく生まれて与えられたこの体。いろんな使い方をしてみようじゃありませんか。そして、「こんなに面白い使い方もあったのか!」「こんなに快適な使い方もあるのか!」という発見を、ひとつでも多く体験してもらえたらなによりの喜びです。
レッスンでは生徒さんの課題に応じて、「こう考えてみるといいんじゃないか?」「こんな事を試してみませんか?」という提案をしています。気に入ったアイデアがあれば、ぜひ使ってみてくださいね。
このシリーズ、全7回でお届けします。
音楽の悩み、ひとりで抱えていませんか?
もしあなたが、
- 音は出るけど、なぜか響かない
- 練習しているのに上達している気がしない
- 正しい構えをしてるはずなのに、しんどい
そんなふうに感じているなら──
メルマガ『バイオリン応援団通信』を読んでみてください。
毎日ちょっとずつ、
演奏の本質に近づいていく考え方や練習のヒントをお届けしています。
いちろーた式の学びは「深く考えさせられるのに、すっと身につく」
今まで読んだどの教材とも違うかもしれません。
👇メルマガ登録はこちらから

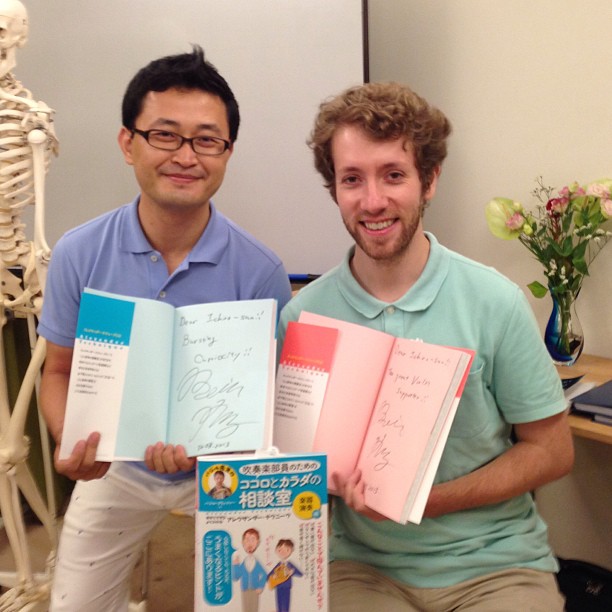

コメント