2013年8月23日 BodyThinking
BODYCHANCE東京、音楽プロコースの第2学期が始まりました。
この第2学期の大テーマは「腕」です。ちなみに、4月から8月までの第1学期は「軸」でした。体幹とか胴体とか、生命維持の根幹を成す器官が収まっている領域に焦点をあわせて、「どんな仕組みが《やりたい》を支援してくれるのか」また、逆に「同じ仕組みであっても、使い方次第で《やりたい》ことを邪魔しちゃう」ということを学んできました。
腕とは?
さて、腕ってなんでしょうね?
腕そのものは、生命維持には不可欠ではありません。腕が無かったとしても、できる活動の可能性はゼロにはなりません。しかし、腕がなかったとしたら、生きようとするうえで思いがけない制約を受けやすくなります。
さて、腕とは?
さて、腕って何でしょうね?
どの部分が腕なのでしょうか?どこからどこまでが腕なのでしょうか?
腕を使っている自分とは?
バイオリンを演奏しようとするとき、チェロをケースから取り出そうとするとき、ギターをチューニングしようとするとき、コントラバスを寝かせようとするとき、あなたの思いは《腕》に何をさせているのでしょうか?
腕がどのような構造を持っているか、どのような動きをすることができるのか……知らなくても演奏はできます。なぜなら、生まれてからいままでの間に、さまざまな生活の局面を通して、動かし方を身につけているからです。でも、もしも、その動かし方が、生まれ持った可能性を使い切っていないとしたらどうでしょう。あるいは、かつて自由に使えていたものがいつのまにか自由さを失って身動きを取れなくしているとしたらどうでしょうか。
解剖学を精密地図として使う
解剖学的な知識を手がかりにして、自分自身のカラダと向き合っていく、自分のやりたい事のために、持ち合わせた可能性のもっとよい組み合わせ方を探求する……それがBodyThinkingのクラスの大きな特徴だと僕は思っています。
あくまでも、やりたいことがあるから、そのために地図を手に入れる。地図の読み方を知る。地図の書き方を学ぶ。そういうことです。
音楽の悩み、ひとりで抱えていませんか?
もしあなたが、
- 音は出るけど、なぜか響かない
- 練習しているのに上達している気がしない
- 正しい構えをしてるはずなのに、しんどい
そんなふうに感じているなら──
メルマガ『バイオリン応援団通信』を読んでみてください。
毎日ちょっとずつ、
演奏の本質に近づいていく考え方や練習のヒントをお届けしています。
いちろーた式の学びは「深く考えさせられるのに、すっと身につく」
今まで読んだどの教材とも違うかもしれません。
👇メルマガ登録はこちらから
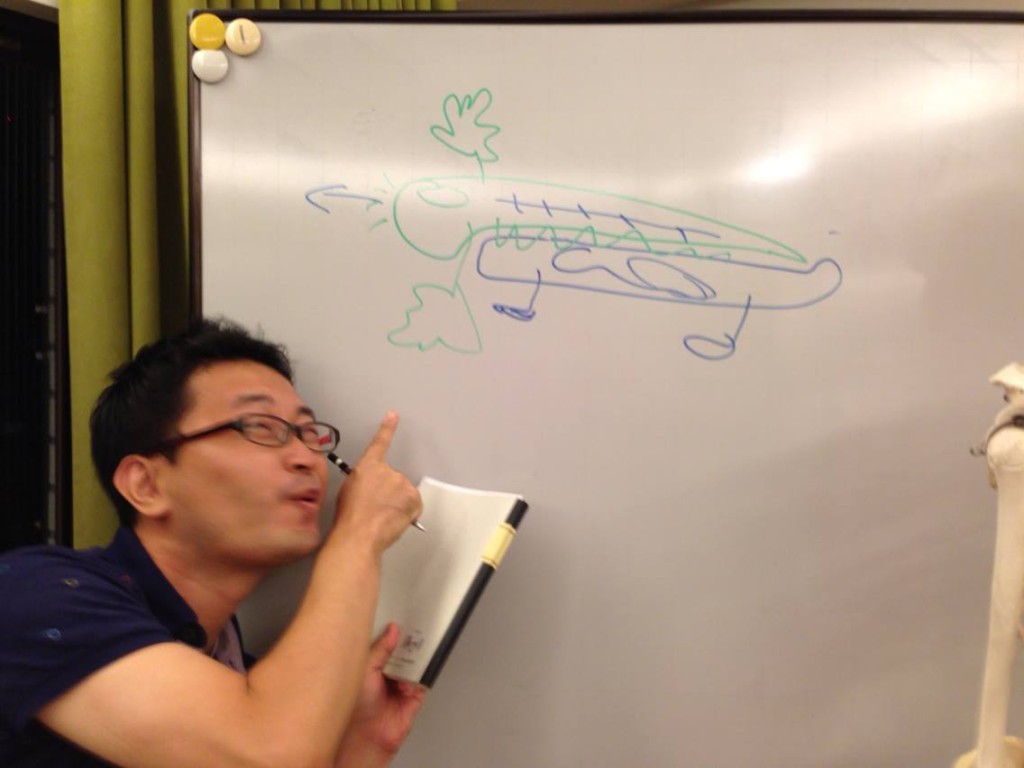
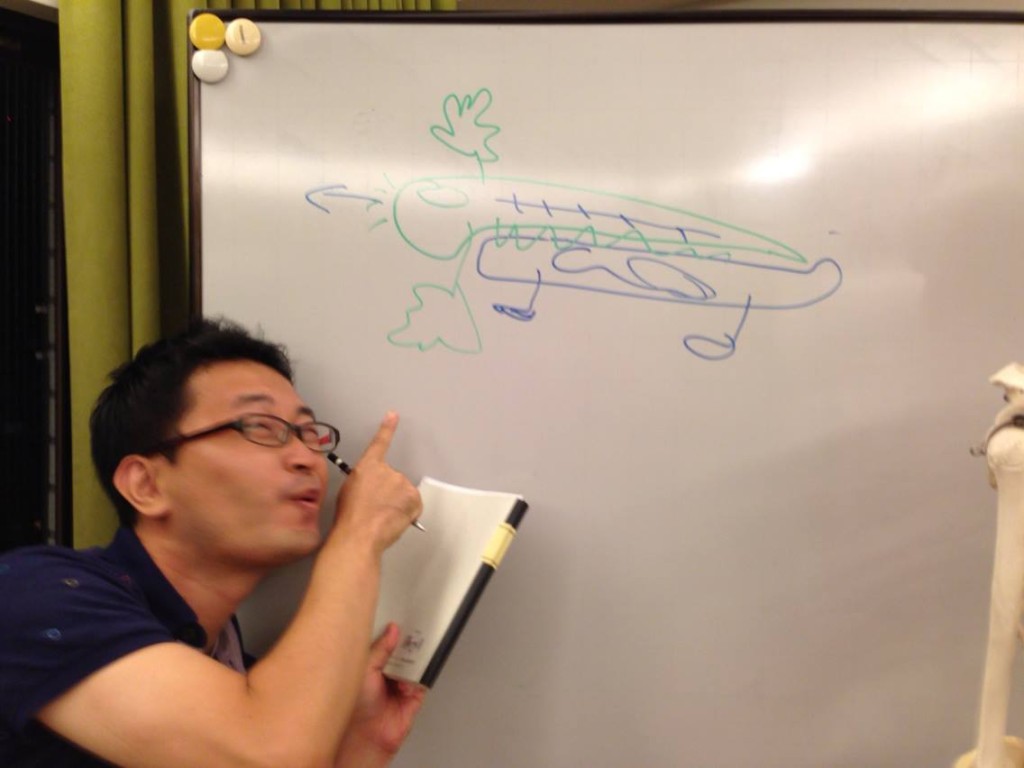

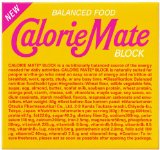
コメント