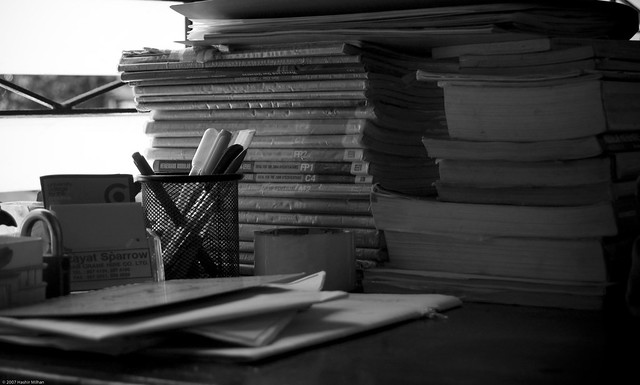【ヴァイオリン演奏の教育学】奏法の観察・分析、教授法など関連しそうなもの(論文・研究ノートなど)を集めてみる(1)
2014/07/16
刊行されている教則本を収集するだけではなく、ほかにできることはないかと、論文など、ほかの人の研究成果を集めてみようと思います。
『ヴァイオリン演奏基礎指導法・研究ノート・1 Research on Teaching Method of Violin Playing Basics 井後勝彦』
ごく初歩の段階についてのノート。
次の段階へとすすめるための判断基準、いわば「みきわめ」についてかいてあるところが秀逸ではないかと思う。
http://harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/hbg/file/9514/20111129105045/g01-09.pdf
『演奏家育成のためのヴァイオリン教授法―― 学習者と教師の観点から ――』
つまるところ、教師は「観察」と「分析」を磨かねばならないという課題にいきつくと結んでいる。同感。
では、どうやって観察と分析を磨けばよいのか。また、それをどう教授すればよいのだろうか?
http://libdspace.biwako.shiga-u.ac.jp/dspace/bitstream/10441/7996/1/kenkyukaronbunshu12pp.33-44.pdf
『ヴァイオリンの指導と静的弛緩誘導法の共通項』
このページの最後の一文は、私がレッスンのときに思っていることと同じであるように思います。
子どもが「楽しいなあ」「またやってほしいなあ」と感じながら訓練をする中で子どもの興味・関心が広がり、その結果として体の機能が向上すればよいと思います。
http://www.geocities.co.jp/Berkeley/8401/sikan/vaiorin.htm
『鈴木鎮一バイオリン指導曲集』成立の背景 —Maia Bangと Elizabeth Fyffeによる Violin Method の分析を通して—
スズキ・メソードを初めとする、3種の教授システムを比較対照した表から、スズキ・メソードの特色が浮かび上がってくる。
導入・初歩から、どうやって技術を発展させていけばよいかを考える好材料ではないだろうか?
http://sucra.saitama-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php/KP18A06-490.pdf?file_id=1661
初期段階におけるバイオリン指導法に関する考察(A study of violin instruction method for beginners)
「バイオリン 教育 論文」にて検索し、見つけた。
もうちょっと読んでおきたいところ。
バイオリンの初歩段階における、教本や奏法解説書のまとめとしては十分と思える内容。
しかし、筆者の意見は検討する必要があると思う。特に、ポジション移動のあたりからは、入念に検討しておきたいところだ。
http://ir.lib.shimane-u.ac.jp/bull/bull.pl?id=8256
バイオリン指導における弓の速度と音の関係(Relationship of bow’s speed and sound in violin guidance)
http://www.sofken.com/FIT2009/pdf/K/K_054.pdf
身体知としての弦楽器演奏のスキル(<特集>音楽と人間)
CiNii 論文 - 身体知としての弦楽器演奏のスキル(<特集>音楽と人間)
以下、抄録
我々は弦楽器演奏を取り上げ,職業演奏家の技を明らかにすることを目的として身体知の言語化の研究を始めた.より具体的には,大きな自由度をもつ右手による運弓動作に着目した.そこでの問題は,最適な軌道を選択すること,および,その軌道を常に再現するためのスキルを身に着けることである.軌道を選択する際に必要となる最適性の基準としては力学的な妥当性および体の可動域などの制約条件を想定した.実際に職業演奏家の体の動きを観測し,その動きの力学モデルによる説明を求めた.さらに,演奏中の生体力学的時系列データを計測し,それらのデータの中から特徴的なパターンを抽出して高度な演奏の秘密を解き明かす試みにも挑戦している.